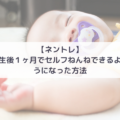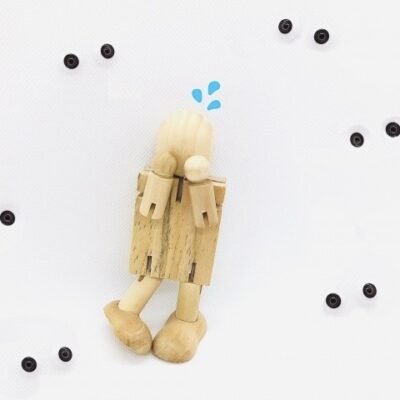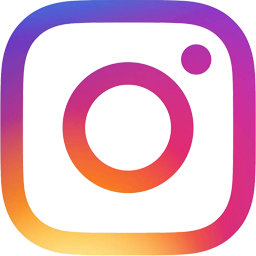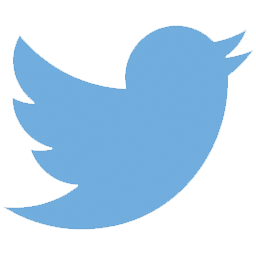赤ちゃんの夜泣き等で、まとまった睡眠時間がとれない日々を経験したママは少なくありません。
私もその一人で、一番辛かったのは「いつまで続くかわからない」ということでした。
個人差がある前提で、経験者ママたちの声を集めました。
みんなに通じていることは、「永遠に続くわけじゃないよ」ということです。
目次
【体験談①】2歳を過ぎても2時間おき

一般的によく言われるように、完全母乳(以後、完母)だったことも影響したのか、
2歳を過ぎても2時間おきに起きてなかなかまとめて寝てくれなかった1人目。
その子は、2歳半を過ぎたころにやっと6時間程度は目覚めずに寝てくれるようになったそうです。
今回お話を聞いたママたちの中で、この子が夜泣き期間最長記録でした。
離乳食が安定してくると睡眠時間が伸びた2人目
1人目の赤ちゃん期よりも、上の子がいる分環境的には騒がしいはずの2人目ですが、
こちらは1歳3ヶ月で8時間通して寝てくれるようになったそう。
ちょうど、離乳食の量も増えて安定してきた時期と重なっていたとのことで、
空腹感があるとどうしても夜泣きの回数が増えるのかな~とお話しくださいました。
【体験談②】1歳半ごろにやっと6時間睡眠に近づいた

私の場合、1人目は1歳を過ぎるまで2時間弱おきに目が覚めてしまっていました。
というのも、呼吸しているか、熱はないか、顔をひっかいていないか、おむつは替え時でないか等々、
空腹以外にも気になるポイントがいくつもあったからです。
その結果、日中もずーっと頭の中に霧がかかったようにぼやーっとしてネガティブ思考。
自己肯定感も爆下がりで、まるで自分が自分でなくなっていくような感覚に陥っていました。
夜間授乳を卒業した頃から6時間程度寝てくれるように
寝不足がもう限界だった私は、夜間授乳をやめることを決断しました。
すると、3日目の晩から1回分の夜泣きが減るように。
そこからは徐々に夜泣きの回数が減って1歳半になる前に6時間程度寝てくれるようになりました。
2人目、3人目も同じ作戦で睡眠時間を確保しました。
2人目は母乳をよく飲む子で、そもそも6時間程度は寝てくれる子で、
3人目は食が細く、授乳中にすぐ寝てしまうので細切れ睡眠タイプ。
タイプが異なる3人でしたが、いずれも1歳過ぎに夜間授乳をやめてからは
夜は5~6時間まとめて寝てくれるようになったのでラッキーでした。
【体験談③】3ヶ月を過ぎたころから6~8時間寝てくれるように
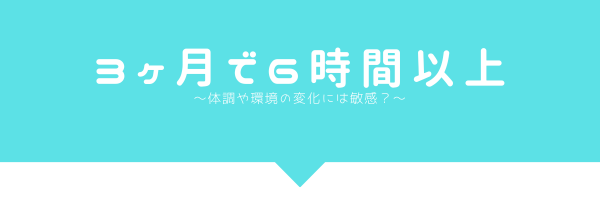
次にお話しくださったママは、睡眠不足に感じたのは最初の数ヶ月だけとのことでした。
お子さんは母乳とミルクの混合で育ち、どちらもよく飲んでいたそうです。
体調や環境が変わると細切れ睡眠に
ただ、風邪をひいて咳で起きてしまったり、
実家や旅行で環境が変わると寝つきが悪く眠りが浅いそう。
赤ちゃんながらに、普段と違うことに気づくんだなぁと
お話を聞きながら感心していました。
【体験談④】寝不足を問題に感じたことはほとんどなかったママも
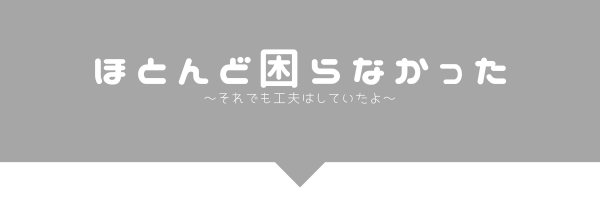
人格が変わったと感じるほど、寝不足に悩まされた私からすると非常に羨ましいお話しですが、
夜泣きで困ったという記憶がほとんどないというママたちもいました。
「3時間おき授乳」は守らない
産院で助産師さんに指導された3時間おき授乳は守らなかった。
ママ側も特に母乳にこだわりもなく、赤ちゃん側もミルクをよく飲む子だったので、
たっぷり飲んでたっぷり寝てというのをただ繰り返していたそうです。
睡眠環境を整える
夜は、遮光カーテン等でとにかく部屋を真っ暗に。
ホワイトノイズを流したり、赤ちゃんにとって快適な室温と湿度管理に
特に力を入れていたというママもいました。
気づかないフリ
ちょこっと声をあげたくらいでは動き出さない。
そのまま自分で再入眠するようであれば、そのままママも一緒に再入眠していたそう。
赤ちゃんがいよいよ顔を真っ赤にして大泣きしだしたら、
やっと抱っこしに行くくらいでちょうどよかった気がするとのことでした。
まとめ
最長で2歳半頃まで寝不足が続いたというママもいれば、
夜泣きで困ったという記憶がほとんどないというママもいました。
お子さんによってもちろん個人差はありますが、ほとんどのママが夜泣き対応の終わりを迎えています。
さらに、ママたちは様々な対策を施していることもわかりました。
先輩ママの知恵を借りることで、状況改善につながれば幸いです。
【ママライターのネントレ体験はこちら↓↓】
とにかくポジティブな夫と、8歳(娘)、6歳(息子①)、4歳(息子②)の3人の子宝と5人暮らし。
「死に際の後悔を最小限にする生き方」を日々模索しています。
正解のない子育てにおいては特に「本当にアレでよかったのか?」と自問自答する毎日ですが、家族の笑顔が第一目標です。
第一子を出産後、親戚も友達もいない地での最初の子育ては非常に孤独なものでした。
自分の周りに“母親”はたくさんいるし、いたはずなのに、この孤独について教わる機会がなかったのです。
私の記事を読んでくださったママだけでも、読んでくださっているこの瞬間だけでも、この孤独から解放されますように。